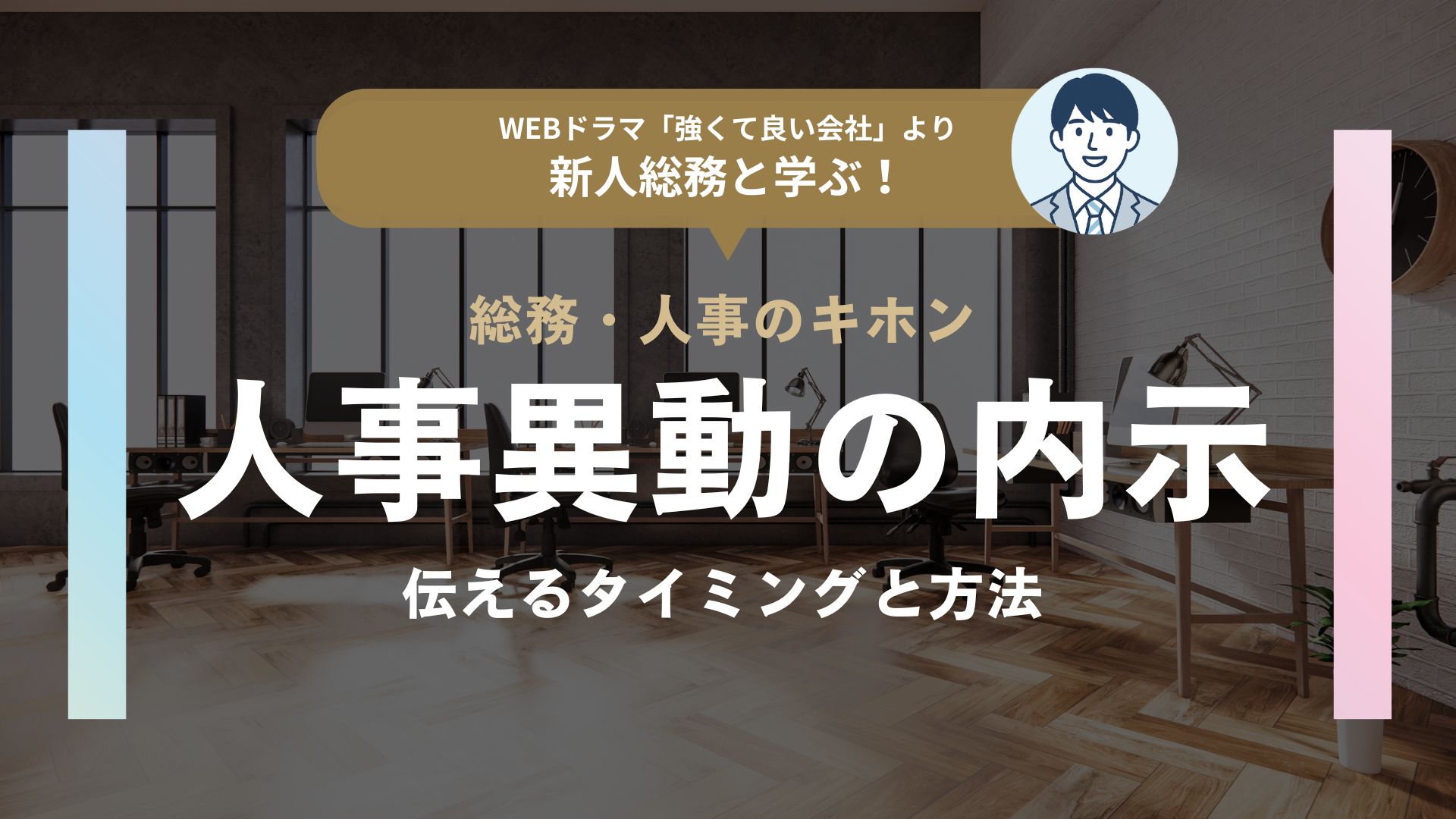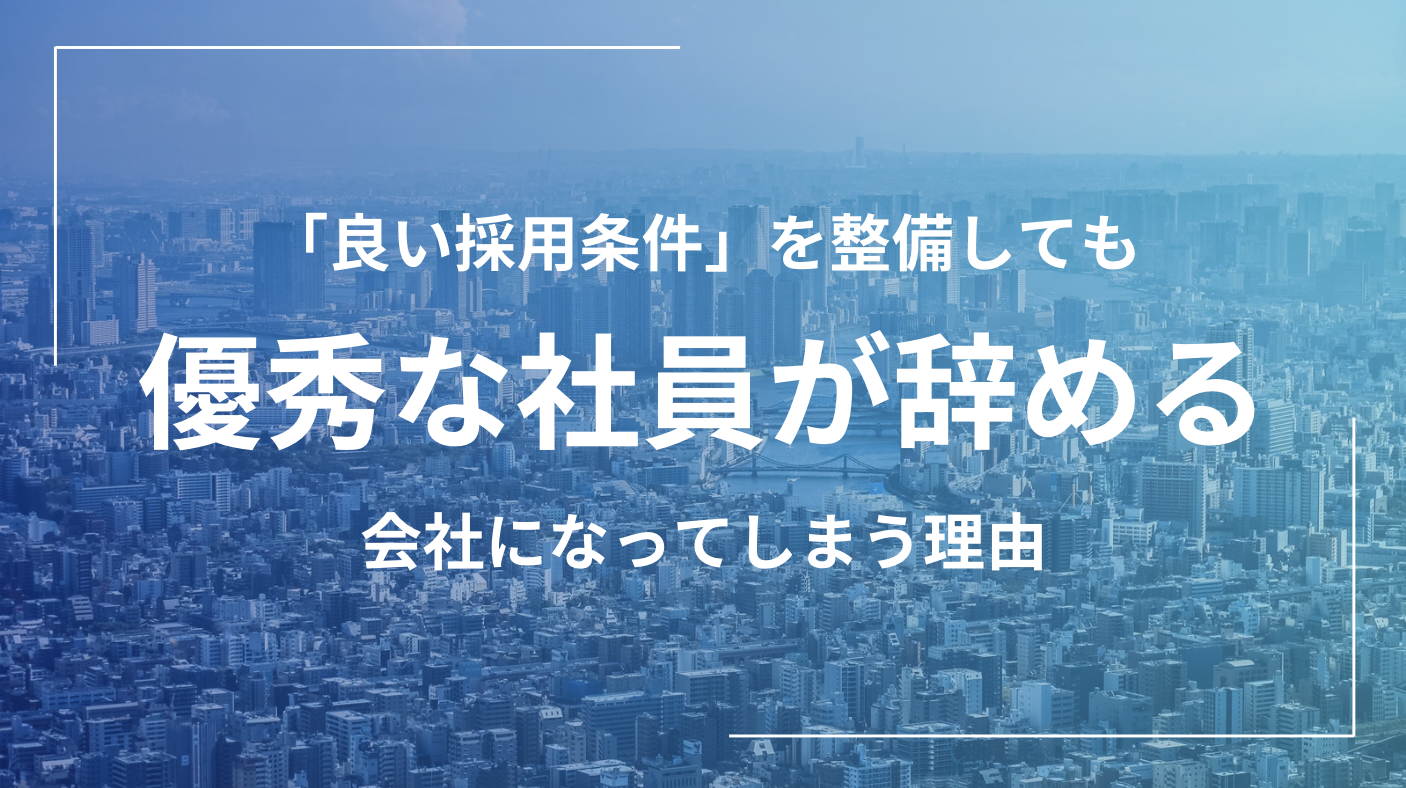組織内の「モヤモヤ」を減らせば、組織は強くなる?
目次
組織内の「モヤモヤ」はどこからくる?
人は、噂話が好き
昔も今も、世の中は毎日のように、さまざまなニュースや噂話で盛り上がっています。
たとえば芸能界の話題などは、有名人が何か一つ事件を起こせば、それだけで一つの番組ができあがるほど、世の中はニュースや噂話にくぎ付けになります。
もちろん、エンタメとして楽しむのであれば問題ありませんが、同じようなことが企業の中で起こると、どうでしょうか。
社内の一つのニュースや噂話によっては、業務にまで影響を及ぼし、生産性が落ちるどころか、場合によっては人間関係に支障をきたすこともあるかもしれません。さらに、業務上のミスや情報共有の不備などが発生し、顧客からのクレームにまで発展してしまう可能性もあります。
このように、ニュースや噂話は結果的に組織のパフォーマンスを低下させてしまうことがあるのです。
会社だからこそ、無駄な話が広がってしまうことも
「社内政治」や「鶴の一声」といった言葉があるように、何を言ったかよりも誰が言ったかが重視されるケースが、企業内ではよくあります。
また、上司の発言がたとえ理にかなっていなくても、そのまま通ってしまったり、正式なルートを経ずに承認されている案件があったりするのも現実です。
こうした役職者や経営陣に関するニュースや噂話も、社内では盛り上がりやすい話題でしょう。しかしこのような話題は、特に組織に与える影響力が大きいため、常に注意が必要です。
では一体なぜ、企業の中で無駄な話が広がったり、噂話が盛り上がったりするのでしょうか。
実は、そのような話をしてしまう人、そういう話に乗ってしまう人には、企業内でのコミュニケーションにおいて必要な3つの視点が欠けているのです。
企業内コミュニケーションに大切な3つの視点とは?
こうした無駄話や噂話が盛り上がってしまわない様に、気を付ける3つの視点があります。

- 事実かどうか
(本当なのか、誤情報なのか) - 適切かどうか
(発言や行動が適切であったかどうか) - 善悪の判断
(それが組織の理念や方針に沿っているかどうか)
この3点が明確であれば、組織内で無駄な話が広がることなく、むしろ伝えるべきことが適切に伝わるようになります。逆に言えば、ニュースや噂話にモヤモヤするのは、そのニュースや噂話に1~3のいずれかが欠けている話題だからなのです。
「事実かどうか」の視点が足りていないと…
たとえば「〇〇さんが降格処分になるらしい」という話題を聞いた場合。
降格の話は特に本人には聞きづらいため、「1:事実かどうか」を確認できず、モヤモヤしてしまうのです。そうなると、仕事に手がつかなくなる人も出てきて、生産性が下がってしまいます。
また、中にはそのモヤモヤを解消するために、真実を知っていそうな人にたどり着きたくて、あちこちでその噂話を尋ね回るようになる人も出てきます。
こうした行動によって噂話はどんどん広がり、社内の生産性はさらに低下してしまうのです。


「適切かどうか」「善悪の判断」の視点が足りていないと…
その他にも、たとえば会議の後に「自分の発言は正しかったのだろうか…」とモヤモヤして、その後の仕事に身が入らなくなることもあるかもしれません。
これは「2:適切かどうか」に関する事例です。
また、会社の方針に対して「自分の考えは合っていないのでは?」と感じるモヤモヤは、「3:善悪の判断」に関する事例なのです。
組織内の「モヤモヤ」を減らすには?
企業内でのコミュニケーションにおいてモヤモヤしそうなときは、その場で次の3点を意識することが重要です。

- 本当なのかどうかを確認する
- 適切か不適切かを判断する
- 善悪を個人の価値観ではなく、組織の価値観で考える
このような習慣や風土を組織内に築いていくことが大切です。
この3つを徹底することで、噂話は減り、生産性が向上し、組織はまとまり、結果として組織力が高まります。
こうした考え方を研修や全体設計の中で浸透させていくことこそが、組織のモヤモヤを解消し、組織力開発の鍵となるのです。
まずは会社の価値観の整理から

全体設計・戦略策定サービス
DREAMIXでは、理念体系やパーパス、そして社風など、会社全体が目指す方向とそのロードマップを一緒に整理しております。
サービス詳細資料は以下から無料でダウンロードしてください。
【 この資料でわかること 】
・全体設計
・戦略策定サービスの特徴
・理想的な会社へのロードマップ
・強くて良い会社とは
・ご相談方法
関連記事